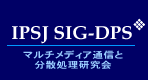第202回 マルチメディア通信と分散処理研究会研究会(DPS)
第108回 情報処理学会 コンピュータセキュリティ研究会(CSEC)
https://www.ipsj.or.jp/kenkyukai/event/dps202csec108.html
■ 日程・開催形態・場所
日時:2025年3月17日(月) 9:30 - 18日(火) 17:20
会場:群馬県庁昭和庁舎 and オンライン
〒371-0026 群馬県前橋市大手町1丁目1-1
https://www.maebashi-cvb.com/spot/1024
■発表時間
発表1件あたり合計20分
内訳は発表15分,質疑5分
■3月17 (月)
<09:30-10:50 DPS: 防災・通信制御>(34会議室)
座長: TBD
1. 避難者間の関係性を考慮した率先避難誘発手法の検討
◯岡本 宙、川上 朋也(福井大学)
2. 災害画像の要約に向けた深層学習モデルのファインチューニングによる被害状況分類の検討
◯吉崎 響、内山 彰、廣森 聡仁、高井 峰生、山口 弘純(大阪大学)
3. RCMSにおける害獣のマルチアングル撮影の高品質化を目的としたロープ配置手法の提案
◯江本 裕紀、勝間 亮(大阪公立大学)
4. 速度制限時のモバイル端末においてWebページの表示を高速化する仮想ブラウザの提案と試作
◯松本 怜也、早川 智一(明治大学)
<09:30-10:50 CSEC: ネットワークセキュリティ>(35会議室)
座長: TBD
5. mDNSトンネリングによる不正秘匿通信
◯小川 真一郎、駒野 雄一(千葉工業大学)
6. 悪意のあるルータを仮定した軽量匿名通信における責任追跡性に関する一考察
◯高田 直弥、吉仲 佑太郎、武政 淳二、小泉 佑輝(大阪大学)、長谷川 亨(島根大学)
7. 軽量匿名通信プロトコルにおけるパス検証の実装
◯河内山 深央、吉仲 佑太郎、武政 淳二、小泉 佑輝(大阪大学)、長谷川 亨(島根大学)
8. 広域スキャンシステムCensysを活用したIoTプラットフォーム探索の試行
◯彭 莎、インミンパパ、佐々木 貴之、吉岡 克成(横浜国立大学)
<11:00-12:20 DPS: ネットワーク>(34会議室)
座長: TBD
9. 投機的プロシージャ処理を導入したモバイルコアにおける障害時のQoE低下回避
◯倉田 真之、鈴木 理基(KDDI総合研究所)
10. マルチホップネットワークにおけるクラスターヘッドの動的選出によるノードの稼働時間の平滑化
◯大沢 恭平、串田 高幸(東京工科大学)
11. Simulation-Based Evaluation of PicoSat Array Distributed Beamforming for Direct-to-Cell Connectivity
◯Tengis Buyantogtokh, Akira Uchiyama, Akihito Hiromori, Hirozumi Yamaguchi (Osaka University), Sumio Morioka, Takahiro Inagawa (Interstellar Technologies)
12. 小型低軌道衛星群を一つのアンテナとして動作させるための衛星間リアルタイム情報伝達機構
◯佐々木 航、安本 慶一、松井 智一、諏訪 博彦(奈良先端科学技術大学院大学)
<11:00-12:20 CSEC: ブロックチェーン>(35会議室)
座長: TBD
13. ブロックチェーンと耐タンパーデバイスを活用した医療情報共有システム
◯松本 太一、髙橋 大成、面 和成(筑波大学)
14. Impact Evaluation on Block Hijacking Attack and Insights for Scaling Solutions
◯Kabuto Okajima (Gunma University), Shin'ichiro Matsuo (Georgetown University), Koji Chida (Gunma University)
15. 複数のブロックチェーンを用いたトレーサビリティシステムの提案
◯角杉 蒼依、面 和成(筑波大学)
16. ブロックチェーンを用いた契約管理システムの開発
◯藤本 浩司、井上 敦司、三淵 啓自(デジタルハリウッド大学)
<13:40-15:00 CSEC: 検知・分類 (1)>(34会議室)
座長: TBD
17. 記号列の組み合わせを用いたステルス化XSS攻撃の検知
◯工藤 諭、中川 みどり、三橋 頼樹、室井 啓冴、牛山 智稀、和泉 大輝、宇田 隆哉(東京工科大学)
18. APIコール対応表に基づく特徴ベクトル化手法を活用したマルウェア検出
◯佐藤 悠弥、青木 渉、石井 龍河、伊藤 峻、加藤 蓮、坂田 竜一、宇田 隆哉(東京工科大学)
19. XSSEDデータセットの適正化とステルス化されたXSSの検知手法
◯貞野 秀明、宇田 隆哉(東京工科大学)
20. 抽象構文木の条件分岐と繰り返し構造を利用した悪性JavaScriptの検知手法
◯遠藤 明恵、宇田 隆哉(東京工科大学)
<13:40-15:00 CSEC: プライバシー (1)>(35会議室)
座長: TBD
21. マルチメッセージシャッフルモデルによる局所差分プライベート行結合データのプライバシ増幅
◯千田 浩司、齋藤 翔太、高木 理(群馬大学)
22. 公平なセントラル差分プライベート等結合プロトコル
千田 浩司(群馬大学)、市川 敦謙、◯紀伊 真昇、三浦 尭之(NTT社会情報研究所)
23. パーソナルデータストアに適したプライバシー保護データ管理・提供システムの実装評価
◯梶田 海成(日本放送協会/東京大学)、山村 千草、大竹 剛(日本放送協会)
24. 秘密計算システムを用いた教務データ分析の実証実験および関係者プライバシーに基づくリスク評価
◯高木 理(群馬大学)、森田 哲之、田村 桜子、田中 哲士、太田 賢治(NTT社会情報研究所)、千田 浩司(群馬大学)
<15:10-16:30 DPS: セキュリティ>(34会議室)
座長: TBD
25. MITRE ATT&CKを活用したシステム設計段階での攻撃グラフ生成と可視化手法の提案
◯森 郁海、板垣 弦矢、島邉 遼佑、森 拓海(三菱電機)
26. トラストゾーンモデルにおける不正情報流の防止
◯中村 繁成(東京電機大学)、Ogiela Lidia (AGH University of Krakow)、滝沢 誠(法政大学)
27. 転移学習を用いたDDoS攻撃対策のための侵入検知方式の研究
◯齋藤 尊、呉 謙、金井 敦(法政大学)
28. 単語ごとのタイピング速度に基づく不正ユーザ検知におけるデータ拡張手法の検討
◯伊藤 拓巳、川上 朋也(福井大学)
<15:10-16:30 CSEC: プライバシー (2)>(35会議室)
座長: TBD
29. PrivBayes+: StaircaseメカニズムによるPrivBayesの性能向上
◯三浦 尭之(NTT社会情報研究所)、竹内 弘史、櫛部 義幸(アーク情報システム)、紀伊 真昇、芝原 俊樹、市川 敦謙、山本 充子(NTT社会情報研究所)、石原 一郎(NTTテクノクロス)、千田 浩司(群馬大学)
30. 合成データ生成における匿名化の適用に関する一検討
◯森 毅(日本総合研究所)、菊池 浩明(明治大学)
31. 差分プライベータな合成データ生成による匿名データ作成の検討
◯菊池 陽、南 和宏(統計数理研究所)
32. プライバシを強化したKey-Value Commitments
◯辻村 都倭、宮地 充子(大阪大学)
<16:40-18:00 CSEC: 検知・分類 (2)>(34会議室)
座長: TBD
33. 垂直連合学習でのパレート最適化を用いた特徴量選択手法の提案
◯磯貝 奈穂、深見 匠、山﨑 雄輔、田村 桜子(NTT社会情報研究所)
34. コントラクトアカウントを活用したデジタル地域通貨への用途制限ルール外付け手法の提案
◯米倉 裕貴、長谷川 悠貴(富士通)
35. PC操作と生体データを用いたセキュリティ疲れの検知と評価
◯中島 佑輔、呉 謙、金井 敦(法政大学)、畑島隆(NTT)、谷本茂明(日本国際学院大学)
36. GANによるデータ不均衡性解消法を用いたNIDSの有効性検証
◯酒井 涼多、樽谷 優弥、宮地 充子(大阪大学)
<16:40-18:00 CSEC: 認識・認証>(35会議室)
座長: TBD
37. Enclaveアプリケーション実行端末を識別するTPMベースの端末認証方式
◯鎌倉 仁、掛井 将平(名古屋工業大学)、白石 善明(神戸大学)、齋藤 彰一(名古屋工業大学)
38. 異なるイラストを用いたパーツごとの動作データ解析による個人識別手法
◯進藤 景、千田 脩介、座光寺 大樹、吉野 泰斗、星野 瑞月、手塚 雄星、宇田 隆哉(東京工科大学)
39. 頭部と両手腕のモーションデータのDTW距離に基づくVRユーザ識別
◯三浦 晃暉、菊池 浩明(明治大学)
40. オンラインターゲティング広告におけるユーザ閲覧履歴入札の数理モデル
◯田口 勇翔、菊池 浩明(明治大学)
■3月18 (火)
<09:20-10:40 DPS: 並列・分散>(34会議室)
座長: TBD
41. NFTで管理されたIPFS上のコンテンツに対するアクセス制御方法の提案
◯松本 光弘(三菱電機)
42.エッジコンピューティングを利用した映像分析システムのデザインパターンと性能検証
◯星野 玲那、坂本 啓、一柳 淑美(NTT ソフトウェアイノベーションセンタ)
43. 並列化した集計処理に対する関係データベースとグラフデータベースの性能評価
◯田村 大樹、河村 美嗣、永井 幸政(三菱電機株)
44. Optimizing Object Storage Performance for Large File Uploading
◯Chung Yi Ting、Nakamura Takaki (Tohoku University)
<09:20-10:40 CSEC: 敵対的攻撃>(35会議室)
座長: TBD
45. 機械学習の中間特徴量に対するモデル反転攻撃の検証
◯浅井 裕希、樽谷 優弥、宮地 充子(大阪大学)
46. 4種類のAudio Adversarial Attackによる攻撃性能検証
◯久保 陽登、加藤 優一、樽谷 優弥、宮地 充子(大阪大学)
47. サイドチャネル攻撃耐性を持つ逆元計算アルゴリズムの改良
◯倉本将吾、宮地 充子(大阪大学)
48. ファインチューニングを用いた電子署名の偽造
◯成田 彩華、大野 裕生、遠藤 凌哉、五十嵐 康平、島多 真輝、鈴木 良輔、宇田 隆哉(東京工科大学)
<10:50-12:30 DPS: モバイルとIoT>(34会議室)
座長: TBD
49. 群知能を用いた移動センシングクラスタにおけるUAV3次元航行実装構成方式とその考察
◯西上 翔磨(関西大学)、橋本 直樹(摂南大学)、新居 英志、四方 博之、滝沢 泰久(関西大学)
50. 移動体環境における物体検出モデルの再学習実行手法
◯陳 明康、合田 憲人(総合研究大学院大学)
51. 自己組織化位置推定方式における評価値とこれに基づく位置精度
◯永井 仁一朗、滝沢 泰久(関西大学)
52. プログラム自動生成のためのIoT用アクチュエータAPI開発
◯野呂 正明(県立広島大学)
DPS特集号特選論文表彰式
<10:50-12:10 CSEC: 暗号>(35会議室)
座長: TBD
53. 耐量子計算機暗号 LWE 暗号の亜種に関する調査報告
◯城戸 良祐、森本 和邦、奥村 伸也、宮地 充子(大阪大学)
54. 素数円分多項式環上のイデアル格子におけるSVPソルバーの提案
◯戸田 和孝、王 イントウ(電気通信大学)
55. カードベース暗号の量子計算による実現に関する研究
◯清原 達成、有田 正剛(情報セキュリティ大学院大学)
56. TFHEのFull Domain Functional Bootstrappingの改良
◯雨宮 岳、藤崎 英一郎(北陸先端科学技術大学院大学)
<13:50-15:50 CSEC: セキュリティマネジメント・SOC>(34会議室)
座長: TBD
57. 構成員の人的脅威を考慮した内部脅威対策手法のプロトタイプシステムの設計
◯小高 佑紀(総合研究大学院大学)、長谷川 皓一(国立情報学研究所)、加藤 雅彦(順天堂大学)、高倉 弘喜(国立情報学研究所)
58. 製品開発者のための効果的な脆弱性ハンドリングの検討
◯寺田 真敏(日立製作所/東京電機大学)、沼田 亜希子、石淵 一三(日立製作所)
59. PC作業における集中度と情報セキュリティリスクの関連性に関する研究
◯石川 陽、呉 謙、金井 敦(法政大学)、畑島 隆(NTT)、谷本 茂明(日本国際学院大学)
60. Kubernetesクラスタを対象とした統合的なセキュリティチェックシステムの検討
◯小川 博徒、寺田 真敏(東京電機大学)
61. インベントリ情報から生成するソフトウェア識別子を用いたIT資産及び脆弱性管理手法の検討
◯峰岡 侑都、寺田 真敏(東京電機大学)
62. コンポーネント依存関係の管理方法の提案
◯山内 克哉、山内 知奈津(日立製作所)、矢戸 晃史(日立ハイテク)、磯部 義明(日立製作所)
<13:50-15:50 CSEC: システムセキュリティ>(35会議室)
座長: TBD
63. 32bit Armバイナリにおける間接参照により呼び出される関数の検出手法の改善
◯矢萩 將馬、山内 利宏(岡山大学)
64. コンテナに対する攻撃からの高速な復旧のためのVM外状態復元機構
◯木本 翔太、光来 健一(九州工業大学)
65. 実行パス異常検知のための制御フローグラフに基づくログ生成機構の自動注入
◯佐々木 康太、掛井 将平(名古屋工業大学)、白石 善明(神戸大学)、齋藤 彰一(名古屋工業大学)
66. Verifiable Credentialsを介してサービス提供者とデータ主体が協働するアクセス権限委譲手法の設計
◯梅田 匠、掛井 将平(名古屋工業大学)、白石 善明(神戸大学)、齋藤 彰一(名古屋工業大学)
67. データ利用制御の柔軟性向上に向けた検証可能なデータ処理環境の設計
◯徳田 祥太、掛井 将平(名古屋工業大学)、白石 善明(神戸大学)、齋藤 彰一(名古屋工業大学)
68. zk-BAN: 柔軟な失効機能を持つ高速な匿名ブロックリスティングプロトコル
◯赤間 滉星(慶應義塾大学)、中塚 義道(スイス連邦工科大学)、植原 啓介(慶應義塾大学)
<16:00-17:20 CSEC: 人工知能・機械学習の応用>(35会議室)
座長: TBD
69. 表層解析情報とCNNを用いたマルウェアの検出手法の提案と有効性の検証
◯佐野 洋明、呉 謙、金井 敦(法政大学)
70. 連合学習の地震動予測モデルへの適用
◯鷲尾 友康(筑波大学)、赤木 翔、鈴木 里奈、早川 俊彦(三菱電機ソフトウェア)、面 和成(筑波大学)
71. 機械学習ベースのNIDSを用いた未知の攻撃分類検知の精度を向上させる手法の提案
◯田中 勁仁、宇田 隆哉(東京工科大学)
72. 機械学習を用いたDRDoS攻撃の早期検知
◯内野 彰紀、宇田 隆哉(東京工科大学)、吉岡 克成(横浜国立大学)
■ 発表申し込み〆切
2025年1月31日(金) 23:59 (JST) ※延長しました
※申し込み多数により早めに受付を締め切りました(1/30)
■ 論文原稿〆切
2025年2月20日(木) 23:59 (JST)
※原則として最大8ページ、6ページ以上が望ましいとさせていただきます。
※締切以降は、原稿の提出、差替、取下げはできません。
※原稿未提出の場合は、発表申込キャンセルの扱いになり、発表できません。
■ 発表申込方法
下記Webページよりお申し込みください.
・DPS研究会の場合
https://ipsj1.i-product.biz/ipsjsig/DPS
・CSEC研究会の場合
https://ipsj1.i-product.biz/ipsjsig/CSEC
※「姓名・タイトルの英文入力欄は必須ではありません」とありますが、姓名・
タイトルについては英文入力欄にも記入をお願いします。
※ 登壇者が学生の場合は「研究会への連絡事項」に「登壇者は学生」と記入してください。
■ 備考
発表申し込みをいただきました方には、後日学会事務局から原稿の依頼をさせていた
だきます(上記申し込みの連絡者の方にご連絡します)。
カメラレディの締め切りは研究会開催日のおおよそ1ヶ月前に設定されます。
詳細については以下のURLをご参照ください。
https://www.ipsj.or.jp/kenkyukai/genko.html
原稿仕上がり枚数は、原則として最大8ページ、6ページ以上が望ましいとさせていただきます。
研究報告用PDF原稿等は、上記の申し込みページでご提出ください。
■ お問い合せ先 ([at] を @ へ変更してください。)
DPS (PC):勝間 亮(大阪公立大学)dps202[at]ipsjdps.org
CSEC (PC):森川智博(兵庫県立大学)csec3cfp[at]csec.ipsj.or.jp
CSEC (LA):千田浩司(群馬大学)csec3cfp[at]csec.ipsj.or.jp
■サイバーセキュリティ研究倫理に関するチェックリストについて(CSEC研究会)
CSEC研究会では、セキュリティ分野の研究倫理の重要性の高まりを受け、
サイバーセキュリティ研究に関する典型的な倫理的配慮を著者らに啓発
することを主たる目的としてチェックリストの活用を進めています。
研究発表に際して研究倫理の観点で懸念がある方は、投稿前にまず
チェックリストを活用し、セルフチェックを実施してみてください。
チェックリストは下記からご利用ください。
https://www.iwsec.org/csec/ethics/checklist.html
[注意事項]
研究報告の完全オンライン化に伴い、研究発表当日の資料は、開催の1週間前に情報
処理学会電子図書館(情報学広場)に掲載されます。そのため、研究報告に掲載される
論文の公知日は、研究発表会の開催日初日の1週間前となります。特許申請の扱い等
の際にはご注意ください。詳細については以下のURLをご参照ください。
https://www.ipsj.or.jp/03somu/kinen_jigyo/50anv/d-library/dl-sig.html
研究会のご案内および最新情報はそれぞれの研究会のWEBページでご確認ください。
DPS研究会 https://www.ipsjdps.org/
CSEC研究会 https://www.iwsec.org/csec/